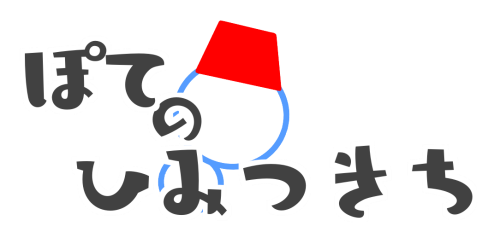ケセドニアへ向かう連絡船キャツベルトへ乗り込み、航海が始まって数日。最初のうちこそ初めて見る海を凝視していた長髪ルークだったが、しばらくするとそれにも飽きてしまい船室に閉じこもっていた。だが、隣室より延々と聞こえてくるうっとおしい呻き声に――誰が何をしているのかなんて誰に聞かなくても判ったし、詳しく知りたくも無い――さすがに辟易した。そんなわけで陰鬱になりかけた気分を切り替えようと甲板に出た彼を襲ったのはいつもの頭痛。
《――やっと……捕らえた》
――否、いつもとは微妙に異なっていた。いつもならば何を言っているのか聞き取れない幻聴なのに、今日に限って一言一句ハッキリと聞き取ることができる。その上、体の自由が全くきかなくなりルークは慌てた。
「かっ、体が……!」
《――お前の力を見せてみよ》
そんなルークの様子など歯牙にもかけず声は淡々と響くのみ。そして声に従うかのようにルークの右手が勝手に持ち上がる。
「なっ、んなんだよっ、これ!」
その手のひらに何か大きな力が集まっていくのが譜術に疎い彼にも判った。それは明らかに破壊の力。
「体が勝手に――ッ」
「ごっ、ご主人様っ、第七音素がいっぱいですのっ、止めないときっと痛いですの!」
「体の自由が利かねぇって言ってんだろーがこのブタザルッ! だいたい止め方なんてわかんねっつーの!!」
急激な音素の増加を察知したのか一緒にいたミュウが本能的な危機感から声高に叫んだが、自由の効かない長髪ルークにはなすすべが無い。
「みゅぅぅぅっ。たいへんですのっ、誰かご主人様を助けてですのっ!!」
ミュウの叫びに応えるかのように、バタバタと複数の足音が響いた。そして慌しく甲板に姿を現したのは短髪ルークと未来ミュウそれにアッシュ。
「みゅぅぅっ、第七音素がいっぱい集まってるですのっ、ちょーしんどーですのっ」
「ルーク! って、これ結構やばくないか? どっ、どうしようアッシュ?」
「――まずい、超振動が発動しかけてやがる! チッ、ローレライの野郎なに考えてやがんだ!!」
普通なら答えの出ない疑問だったかもしれないが、それはアッシュが腰に佩いていた剣からもたらされた。
《うむ。あの時は初めてまともにルークとコンタクトが取れて有頂天だったからな。嬉しさのあまり記念に超振動でも撃っておこうかと。あちらの私も気持ちとしては同じなのではないか? 何しろ七年かけてようやっと――》
つい先程、アッシュの剣――ローレライの鍵に未来のローレライが宿っているのが判明したのだ。どうやら今まで全く存在を気付いてもらえなかったことに腹を立てて不貞寝していたらしいのだが、気づいてもらえた途端に機嫌が上昇したらしく今までの沈黙っぷりが嘘であるかのように饒舌になっていた。
「――どんな思考回路だこの天然意識集合体ィィーーッ!! あの時俺がどんだけ恐怖したかわかってんのかッ!?」
《そうなのか? それはすまなかったな。次があれば善処することにしよう》
「うがぁ~~ッ、そ・う・い・う・問題じゃぬぇーーっ!」
抜き身のまま持たれている剣――と言ってもローレライの鍵はどう見ても鈍器なのでこの表現はおかしいかもしれないが――に向かって怒鳴る姿は端から見るとえらく滑稽ではあったが、本人たちに自覚はない。
「てめぇらくだらねぇ言い合いは後にしろッ、今はあの屑をどうにかしてやるのが先だ!」
「おいコラてめー、アッシュ! こっちに聞く余裕が無いと思ってんだろーが聞こえてっぞ! 屑なんて呼ぶなってのッ!」
「みゅっ? ご主人様けっこう余裕あるみたいですのー」
「ばっか! いま自由がきくのは口だけなんだっつーの!! つーかお前ら、このワケ解んねーのが止められるんならとっとと止めやがれ!!」
長髪ルークの自分本位な態度に一瞬だけ眉間の皺が深くなったアッシュだったが、この傲慢さの何分の一かでも短髪ルークに還元できたならと複雑な心境になる。それはともかく、ここで超振動が発動するのは果てしなくまずい。ローレライも手加減くらいはしているだろうが、超振動に慣れない長髪ルークが制御を誤れば最悪船が沈む。だからアッシュは最も容易に問題を解決できるであろう意識集合体に声をかけた。
「……ローレライ、同一存在のよしみでヤツを止めろ」
《無理だ。あちらの方が干渉力が強い》
「チィッ。肝心な時に役に立たねぇなっ、こんの役立たずがッ」
《そんな事を言われても無理なものは無理だ。今の私は鍵に封じられていて、それなりの力しか発揮できんのだから仕方なかろう!?》
「なら説得するなり何なりしろッつってんだこの天然っ! テメェは力ずくしか能がねぇのかよっ?」
《能がないとは失礼な! 所詮、自然界など弱肉強食の世界なのだから力ずくこそ世の摂理だろう!》
「開き直るなッ!!」
アッシュと鍵が言い合いをしている間にも長髪ルークの掌には力が集まり続けている。臨界点は近づくばかり。このままでは下手をすれば船が沈みかねないというのに一同にはあまり危機感が無かった。
「ああああっ、アイツら全然アテになんねぇーッ! 俺がやらなきゃ俺が……ええとっ、とりあえず落ち着いて深呼吸だルーク! でもって全身で音素を感じ取るんだっ、そしたらたぶんなんとかなる!!」
「だぁぁっ、こんなんなってるっつーのに落ち着いてられるかぁっ! つーか音素を感じ取るってワケわかんねーし、大体たぶんてなんだっ、たぶんって!!」
「えーっと……どーにもならなかったら俺の超振動ぶつけて相殺すればなんとかなるよーな、ならないよーな?」
「どっちなんだよ!? てか何とかならなかったら俺はどーなるんだっ!?」
つーっとそらされた短髪ルークの目線と頬を伝った一筋の汗に、不吉な予感がよぎる。
「ちょ、マテっ、おまっ、何で目を逸らすんだ!?」
「大丈夫! ほら、俺たちって本番に強いし!! お前はやればできる子だってガイが言ってたし、ティアも飲み込みが早いって褒めてくれた!!」
「なぐさめにもならぬぇーーッ!!」
「なんだかとってもぐだぐだですの……」
「でもご主人様とアッシュさんとローレライさんがいますの。だからたぶんなんとかなると思いますの!」
「みゅ、それなら安心ですの! それにしても未来のボクはとってもご主人様とそっくりですの」
そんなこんなで混乱すること数分。結局は鍵の力を借りて一時的に長髪ルークと回線を繋いだアッシュと短髪ルークがなんとか超振動を制御して事なきを得たのだった。
* *
「さて皆さん、無事にケセドニアへ到着したところで一つ。この先、円滑に事態を進行させるためにパーティーメンバーをシャッフルしてみてはどうかと提案します」
ジェイドの言葉から判るとおり一向はなんとか無事にケセドニアへと到着し、これから街の中を横断して現在地とは反対側にあるキムラスカ領事館へと向かおうとした矢先だった。
「……相変わらずあくどいな、眼鏡」
「いえいえ、私はただ災いの目は早々に刈り取るという考えの元に行動しているだけです」
「……」
「それで大佐、どのような分け方をなさるおつもりですの?」
「それなのですが、モースの横槍は封じましたが六神将が残っています。となると、彼らが将であるヴァンを取り戻そうと躍起になる事が予想される。それに親善大使一行が到着するまでにアクゼリュス住人の避難も進めておきたい所なんですが……」
「はいはーい、大佐ぁ。イオン様が狙われる可能性がまだあるんじゃないかってアニスちゃんは思うんで、過去組の戦力は増やしといたほうが良いと思いまーす」
「い~い所に気付きましたねアニス。過去組の話を聞く限りでは、どのセフィロトも未だダアト式封呪が解呪されておらずイオン様が狙われる可能性も未だに高い。……ですがイオン様は2人いらっしゃいますから、もしかすると何処かの勘違いした人間が未来組の方へと向かう可能性も否定できません。戦力は均等に分けるべきと判断しました」
「……おい、えーっと未来のジェイド。なんか訳わっかんねー言葉がいっぱいで話が見えねーぞ」
「その辺は後でじっくり解説して差し上げますよ、ルーク」
「……て事は、お前は俺と一緒に来るってことかよ」
心底嫌そうに呟く長髪ルーク。主にヴァンいぢめの指揮を取っていたのは未来ジェイドだと知っている身からすれば、もう一回あるという船旅の間中またもやあの悲惨な現場を見るハメになるんだと思っただけでテンションは急下降だ。
「ほぉ、中々に勘がいいですねぇ。ちなみに私とガイとアッシュがバチカル帰還組に加わり、代わりに過去組の私とガイには未来組のルークたちと共に一足早くアクゼリュスへと向かっていただくというプランを考えています」
ジェイドとしては今後の手間も考えて、道中セフィロトの操作も行いたい所だったがまだ第五セフィロトのアルバート式封呪が解けていないため、どうにも確実性に欠ける。
「待て待てっ。眼鏡テメェ、バチカルに混乱を巻き起こすつもりか!? 俺たちの時代ならともかく、今の時点で俺と屑が一緒にバチカルに帰った日には何が起こるか判らねぇテメェじゃねぇだろ!?」
「はっはっは。それならば貴方が影ながらこっそりとバチカル入りすれば済む問題じゃないですかぁv」
影ながらこっそり街に入る時点で、すでに同行という前提が崩れている。けれど内密の行動とはいえファブレ家嫡子とローレライ教団の最高指導者が城下入りするのだから、軍部の要職の者たちが港まで出迎えに来るだろう。そんなところに一人しかいないはずのファブレ子息が二人もいたら要らぬ混乱を巻き起こすのは当然必至で、ジェイドの挙げる案は理にかなっている。かなっているが……。
「それは……俺が一緒に行く意味はあるのか……?」
アッシュが呟くのも無理は無かった。
「大いにありますとも。不測の事態が起こった場合の予備戦力として、貴方には存分に働いてもらうつもりですv ……あ、ローレライの鍵は短髪の方のルークへ預けてくださいね」
「――待て、なんでそうなる?」
「今のルークはロクな武器を持っていないんですよ」
それとも貴方はシルバーソードなんていう今の彼にとって棒きれに等しい武器で戦いに備えろとでも言う気ですか? 鬼ですねぇ。すっかりルークに甘くなった死霊使いが満面の笑みでネチネチとのたまう。かくいうアッシュのほうも少なからずルークには負い目があるものだから強く抗議ができなかった。ロクな武器が無い状況での戦闘の大変さは身をもって知っている。なんたって間接的な死因だ。
「ぐっ、だが……」
「鍵には以前と違いローレライが宿っていますから、何かの役には立ちそうですしねぇ。……障気の中和とか、障気の中和とか」
《こら待て。その、なんだかオマケのような扱いは納得いかんぞ、死霊使い!》
さらに内心でジェイドは、あわよくばローレライを使って魔界の障気もまとめて中和できないものかなんて考えていたりする。もちろん本人の意向など無視して、だ。ローレライには人の機微に疎いところがあるためそんなジェイドの思考に気付いていなかったが、果たしてそれは本人にとって良い事か悪い事か。
「アッシュ、貴方には教団支給の剣があるでしょう? 何せ鍵を手に入れた後……少なくともキノコロードではそれを使っていたようですし問題なんてないですよね?」
「……心許なさすぎだ」
《無視か!? 私の存在は空気と同一かっ!?》
「心許ないなら闘技場で上級戦に参加したらいいんじゃねーか? ソウルクラッシュなら鍵より破壊力あるし」
今ならまだ闘技場やってるはずだから行ってみたらいいんじゃねぇ? なんてのんきに告げる短髪ルーク。当然のごとくローレライの言葉は無視だ。背後では「バチカルに闘技場があるなんて聞いてないぞ!」と長髪ルークがガイを睨みつけ、対するガイの「いや、だってなぁ? お前、闘技場があるなんて聞いたら屋敷から抜け出しかねないだろ?」なんて返答に、言葉をつまらせるという微笑ましいやりとりが交わされていたりした。
ソウルクラッシュ? と首を傾げたアッシュだったが、少し考えてエルドラントでの一騎打ちでルークが使っていた剣がそれだったと合点がいった。
「ははは、ルーク。そもそもアッシュは目立った行動が取れないっていう前提を忘れてるだろ?」
「あ、そうだっけ。じゃあどうすっか……そうだ! シンクみたく仮面着ければいいんじゃね?」
「お前は馬鹿かっ!? 仮面を着けたところで髪の色でモロバレだろうが! ここはファブレの膝元なんだぞ! というか俺は闘技場なんざ行く気はねぇッ。称号使って荒稼ぎした挙げ句にブラックリスト入りしちまうようなお前らと一緒にするな!」
「おやおや、何気にこちらの事情に詳しいですねー。もしやストーキングでも?」
「きっ、気色の悪い事をいうんじゃねぇ!! 偶々だっ、そこの馬鹿に連絡しようと思って回線をつなげたら……!!」
まさか人恋しくなって時々こっそりとルークとの回線を繋いで見物してましたとは言えないアッシュだった。
* *
「今回、ファブレのご子息が出奔したのはこの髭が原因です。既に自由は奪ってありますので、とっとと牢獄なり何なりにぶち込んでおいてください」
バチカル港にて船を下りての第一声がそれだった。
やけに和やかな表情で告げた未来ジェイドが示した先には、何処から持ってきたんだと問わずにはいられない古びたリヤカーが一台。その中では縄でグルグル巻きにされミノムシのようになったヴァンが寝息を立てていた。時折「メ、メシュティアリカっ、そんな目で私を見ないでくれッ」とか「兄さんが悪かったからっ」なんていう呻き声とともにクネクネと身をよじらせたりするものだから、ルークを出迎えに来ていたセシル将軍やゴールドバーグ将軍それに一般兵士の皆様は顔を引きつらせるばかり。
「はぁ? 俺が屋敷から飛ばされたのってお前らが――――ふごふごっ」
「はいはい。お前の言いたい事は判ってるがここは黙ってようなー、ルーク。……旦那に逆らうと後々やばいってのは判ってるだろ?」
ただ一人、ジェイドの言葉に長髪ルークが眉を顰め文句を言おうとしたが即座に未来ガイによって口をふさがれた。そして小声で呟かれた後半のセリフに恐怖する。死霊使いの名が伊達ではないことをこの数日で長髪ルークは思い知っていたのだ。主に船旅の間延々と行われていたヴァンいじめによって。
「あぁ、そうそう。当然の事ながら譜術防止措置は基本ですよ~。あと牢の鍵は溶接しておくのがオススメですv」
「それは……少しやりすぎなんじゃ…」
過去ティアが呟いた。特に被害を被っていないせいか彼女はいまだヴァンに同情的であった。ティアの心情や経過は未来ジェイドも未来ガイもあの旅の中で嫌というほど傍で見ていたので咎めることはない。ただ、このまま彼女の主張を聞き入れて手を緩めた日には後で死ぬほど後悔する事になるだろう事は確実なので、彼女の心情その他諸々を理解してはいてもその希望を聞き入れることはまず無い。もっとも未来ティアがこの場にいたなら絶対にジェイドたちの意見に賛同していただろうが。
「ハハハ、吹っ切れてないティアは甘いなぁ」
「ええ、ちょろあまですねぇ」
「ちょろあまでも何でもいいんですっ。大佐、さすがに鍵を溶接してしまうと兄は一生牢暮らしになってしまいます! いくらなんでも――っ」
「――良いじゃないですかー、一生牢暮らし! 国が血税まで使って面倒見てくれますからねぇ。仕事をせずとも死ぬまで食いっぱぐれる心配が無いなんて、陛下に扱き使われる老体の私からすれば羨ましい限りですよ」
ま、私はまっぴらゴメンですが。
過去ティアの兄を想う必死の訴えも、毒の溢れる返答にバッサリと切り捨てられた。しれっと追加されたコメントを聞いて「うっわ、コイツ本気で鬼だ」と思わず長髪ルークが声に出す。口にこそ出さなかったものの良識あるキムラスカの軍人たちも同じ思いだった。
結局ルーク失踪にヴァンが絡んでいるという容疑があった為に投獄は実行されることになったが、溶接はやりすぎということでごく普通の牢が使用されることになったのだった。
* *
王への謁見を無事に済ませファブレ邸の食堂に入ったルークたちを出迎えたのは、コバルトグリーンのドレスに身を包んだナタリア。彼女はルークの顔を見るなり顔を綻ばせて歩み寄ってきた。
「ルーク! 帰ってきてらしたのね」
「げっ、ナタリア……」
「げ、とは何ですの? 久しぶりに婚約者に会った殿方のセリフではありませんわね」
「……婚約者婚約者って口うるさいってことはナタリアはナタリアなんだよな?」
「何なんですの、藪から棒に。私は私ですわよ?」
「……いや。ふとお前が先回りした未来のナタリアだったりしたら――なんつー考えが浮かんできちまって……」
「ルーク……そこまで疑心暗鬼になって……」
ブルブルと周りを窺う長髪ルークに未来ガイは思わず涙する。……まぁ、あれだけ女王様なナタリアの所行を目の当たりにすれば当然と言えば当然か。改めて自分たちが彼の前でやったことを思い返すとロクな事してないなとガイはひとりごちる。ナタリアもティアも、ヴァンさえ絡まなければそう過激でバイオレンスな行動に走らない事をガイは良く知っている。二人ともどちらかと言えば平和的解決を望むタチだから、誤解が解ける日がくれば良いんだが。そんな事を思う。
「ルーク、随分と怯えているようですけれど未来の私が何かしまして?」
ルークたちの内心など知るはずも無く首を傾げる過去ナタリア。一応の事情は聞いていても、さすがに旅の最中にバイオレンスが繰り広げられただなんて想像もできないに違いない。だいたい現時点で史実とはかけ離れ始めているから、彼女の持つ情報はあまりアテにはできなかったりする。そこにサッと一歩ルークの前に出たジェイドがしれっと告げた。
「いえ、別にルーク様はナタリア様に怯えている訳ではありませんよ。単に外の世界が予想外に過激だったので様子がおかしいだけですv」
それを聞いた過去ナタリアは目を見開いて「まぁ! そうだったんですの? …よほど困難な帰路でしたのね!」と大仰に驚いた。
オイオイ、ナタリア話題をすり替えられてるぞとおくびにも出さずガイはツッコミを入れる。ちなみに六神将によるタルタロス襲撃が無かったこの歴史において、ルークが遭遇した『過激』な出来事にはもれなく未来組が関わっているのは言うまでもない。
そこで、ひとしきり驚いたナタリアはやっと見覚えの無い軍服を着た人物――ジェイドに気がついた。
「あら、そういえば貴方は…?」
「私はマルクト帝国第3師団師団長ジェイド・カーティスと申します」
「貴方があの死霊使いと名高い? 思っていたよりもお若い方なんですのね」
「いえいえ、最近は寄る年波に勝てず若者のペースについていくのがつらくてつらくて」
和やかに姫と軍人の会話が進んでいく中、脇にどかされた一行はヒソヒソと密談をはじめた。
「……私にはつらそうには見えないのだけれど。大佐はルークより動きにキレがあるし」
「ふん。どーせ俺はジェイドに勝てねーよ」
「ルーク、そうくさるものではないですよ。今は無理でも努力を続ければきっとジェイドに勝てる日が来ます」
「で、俺が強くなった頃にはアイツも更に強くなってて返り討ちかよ?」
ルークの辛辣な切り返しにイオンがうぅっと口ごもる。そこに、あ、とアニスが思い出したかのように口を開いた。
「そういえば外見的には若くみえるから忘れがちだけど総長よりも年上なんだよねー、大佐って」
そういえばそうだったと一同。だが世間の情報に疎かったために知らなかったルークだけはマジかよと驚愕の表情を浮かべた。世間の仕組みもあまり勉強していなかったのも手伝ってか、カイツールではヴァンに敬語で話しかけられるジェイドを「なんで師匠はコイツに敬語なんかで話すんだよ。年上なのに」なんて面白くない心持ちで眺めていたのだ。
「あの旦那は四十代間近だからまったくの嘘って訳じゃないと思うぞ。外見が全く変化しないから忘れがちだが」
「四十って……まじかよ。しかも外見が変化してないってホントに人間か?」
俺、アイツが人の生き血吸ってるとか人間じゃないって言われても驚かねーぞ。そうして着々と長髪ルークの中でジェイド人外説が組みあがっていくのであった。
そして最後までヴァンの行方に関する問いが発せられることが無かったのだが、誰も気付きはしなかったそうな。果たしてヴァン師匠はキムラスカの地下牢から脱出できるのか!?