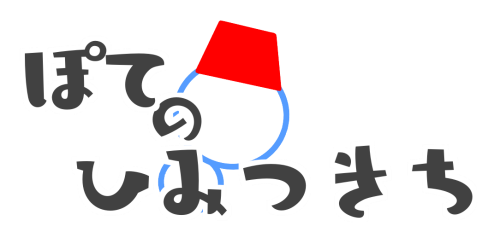「ぐぁっ、頭いてぇ……」
原因不明のひどい頭痛に立っている事もできずルークは床にへたり込んでしまった。七年前に誘拐されて以来続くこの頭痛には何度も襲われているというのに一向に慣れることができない。
《我……に……わ――じく……よ》
しかも近年では何が言いたいのだかさっぱり聞き取ることのできない幻聴まで聞こえるようになってきていて、腹が立つ事この上ない。言いたい事があるならハッキリと言いやがれってんだと毎度毎度罵倒するのだが、あちら様に伝わっている様子は無い。全くの一方通行。
「くぅっ、一体……何だって――」
それもこれもマルクトの奴等のせいだッ! なんで俺がこんな目に遭わなきゃなんないんだっつーの!!
イライラも絶好調に達して、今にも物に当り散らそうかというその瞬間――
――どすん。
「へ?」
何か重いものが目の前に落ちる音でハッとする。気がついたら不思議と頭痛もいつの間にか治まっていて、その事実に少々腹が立った。こんなしゃっくりみたいに簡単に直るものだったのかよ、この程度で直るって言うなら今までの俺の苦労って何だったってんだ。一通り悪態をつくとルークの次なる興味は目の前でイタタと床に打ちつけた腰をさする人影へと移る。
そしてルークは仰天した。
「痛ーっ、ったく。ココどこだよ……って俺の部屋?」
なにせ目の前に座り込んでいる人物は、足の先から頭の先まで鏡に映るかのごとく彼とそっくりだったのだ。呟く声すら同じ。違うのは髪の長さと目つき、それから服のくたびれ具合ぐらいか。
「な、なななななななななななな!!!!?」
「うっせーな……って、ええええええええええ!!!!!?」
声を上げたルークに、座り込んでいたそっくりさんもようやく相手の存在に気付いてお互いに指差しつつ硬直。すかさずバタンと勢いよく窓が開かれ二つの影が飛び込んできた。
「「ルーク!! 大丈夫かっ!?」」
これ以上ないほどに心配顔をして飛び込んできたのは二人のガイ。彼らもまた双子のようにそっくりで、片方はルークが良く知るおなじみの格好をしたガイ。もう片方のガイはゆったりとしたジャケットに緑のシャツという、屋敷の中ではあまり見ないラフな格好。
「「………ガイが二人?」」
「「………ルークが二人?」」
二組のルークとガイはしばし呆然と向かい合う。
そして真っ先に再起動したのはラフな格好をしたほうのガイだった。
「ルークッ!!」
彼は突如叫んだかと思うと、髪の短いほうのルークへぎゅうっと力いっぱい抱きついた。そしてポフポフと彼の体を軽く叩いて、そこに存在していることを確かめるかのように確認する。
「お前ちゃんと生きてる……よな……? 生きてるんだよな? 音素乖離とかしてないよな?」
「えと、俺の知ってるガイ……なのか? あれ、ガイお前なんかちょっとやつれてねぇ?」
「あれから二年も経ったんだぞ。お前がなかなか帰ってこないもんだから俺は心配で心配でッ!」
なのにジェイドもピオニー陛下も遠慮なく俺に仕事を押し付けてくれるもんだから……。ブウサギの世話とか書類整理とかブウサギの世話とかキムラスカやダアト果てはユリアシティとの外交とかブウサギの世話とかその仲立ちとかブウサギの世話とかブウサギの世話とかブウサギの世話とか!! しかもピオニー陛下ときたら俺のブウサギ飼育レベルが上がったことを敏感に察して新しいブウサギを連れてくるんだよッ、そのせいで俺の負担は増える一方!! 今じゃジェイドとネフリーとゲルダとアスランとサフィールとルークとアッシュとガイラルディアとメリルとアニスとメシュティアリカの総勢十一匹!!
そりゃ、俺でなくてもやつれるってもんだろ!?
「……あー、その、ごめん?」
血の涙を流す勢いで迫るガイに、ルークは平謝りするしかなかった。ピオニー陛下もジェイドも絶対面白がってやったんだろーなぁと他人事のように思いながら。
「だぁぁッ!! お前ら一体何なんだよっ!! それに何で俺たちにそっくりなんだっ!?」
短髪のルークたちの感動の再会にしばし呆然としていたが、長髪のルークが癇癪を起こして喚きだした。
「そっくりって言われても本人だしなぁ?」
「だよな、本人だもんなぁ」
けれど何でと問われても答えようがなく、短髪のルークたちは言葉を濁すばかり。しかし何かに気付いたのか通常の格好をしたガイの顔からみるみる血の気が引いていった。
「ま、まさか……ドッペルゲンガー……!?」
「ンだよ、ガイ。その、どっぺるなんたらって」
普段ならすぐにルークの疑問に答えてくれるガイなのだが今回ばかりは動きも無く、答えは期待できそうに無い。だが今回に限っり彼は二人いた。
「ガイ、知ってるか?」
あちらのガイから答えが期待できないならば、こちらのガイに聞こうと思いついた短髪のルークが口を開いた。幸いこちらのガイは怯えも無ければ、顔色も平常通り。長髪のルークも聞き耳を立てていたりする。
「……あぁ、昔聞いた怪談さ。なんでも、もう一人の自分を見たら数日のうちに死んでしまうとかなんとか。もう一人の自分が入れ替わるために殺しに来るんだ、なんていう説もあるな」
「……なんつーか俺とアッシュみてーだな、それ」
「ルーク、お前は気にしすぎだ。だいたいお前もアッシュも死んでないだろ?」
「……何言ってんだよガイ。アッシュは――」
「いや、死んでないってのもちょっと違うか。……詳しいことは後で話してやるよ」
それにしても自分はあそこまで怪談に弱かっただろうか? 女性に弱いのは嫌というほど自覚してるが。真っ青になっている過去の自分を見てガイは嘆息する。そういえばこの怪談を教えてくれたのは誰だっただろうかと記憶を探って納得がいった。
――姉上だ。この話をしてくれたのは。
確か怖がりであった幼いガイに、怖がりを克服させるとかいう名目でもっともらしく語ってくれた話の一つがコレだった。あまりにもリアルに語られたソレが幼いガイの怖がりを更に増長させたのは言うまでもない。人には意外な特技の一つや二つはあるものなのだろう。
「あー、その、なんだ。俺たちはドッペルゲンガーなんかじゃないってのは断言するから落ち着けよ、ガイ・セシル」
「俺は落ち着いてるっ。けどお前たちが本当にドッペルゲンガーじゃないって言う証拠はないだろう?」
よほど疑り深いのか、それともマリィの話によるトラウマが根深いのか……ガイが俺たちに戦う気は無いよと、両手を挙げて降参の意を示しても警戒は解かれない。
「ドッペルなんたらじゃなかったらお前ら何なんだよ?」
「ま、ちょっとややこしい事になってるからなぁ。俺のことはガイラルディアとでも呼んでくれ」
躊躇無く告げられたガイ言葉に、通常の格好をしたガイの肩が目に見えて震えた。目は見開かれ、お前は……と音にならない声が口から吐き出され消えていく。
「なんつーか舌噛みそうな名前だな。……つーか省略したらどっちにしてもガイじゃん」
「名前が二つあるとこういう時に便利だよなー」
そして何も知らぬが故の感想と、全てを知り乗り越えたが故に言える呟きだけが響いた。
□なにこれ□
――二組のルークとガイというありえない邂逅から数十分。ルークとヴァンが稽古をしている時にそれは起こった。
「ヴァンデスデルカ覚悟ッ!!」
突然現れた侵入者は、栗色の長い髪で片目を隠し黒い教団服を着た少女だった。彼女は音も無く取り出した小さなナイフを数本ヴァンに向けて投げると同じ方向にダッシュし手に携えていた杖を力いっぱい前に突き出す。が、ヴァンはその一撃を譜歌で動きが鈍っているとはいえ難無く受け流し、その上で口を開いた。
「やはりお前かティアっ。だが何故ここにいるのだ!」
響き渡っている歌を歌える者は限られているから侵入者が姿を現す前から正体は察していたが、遠く離れたユリアシティにいるはずの妹が何故ここにいて自分に襲撃をかけているのか。しかもえらく殺気立っている。
「……自分の胸に聞いてみるといいわ兄さん」
もしや先日ユリアシティでのリグレットとの会話を聞かれたのか?
ヴァンがとっさに浮かべたのはそんな考え。それならば自らの動きを察して此処に現れたのも判らないではない。……だが、この明確な殺気。あの会話だけでここまで射殺さんばかりの視線を向けられるものなのだろうか。あの時に話していたのは外殻を落すという事項くらいなもので、たしかに責任感の強い妹がここにやってくる理由にはなるのかもしれない。だがやけに黒いオーラを漂わせながら告げてくるティアの姿を見ていると、いま彼女が此処にいるのは責任感とか使命感というよりは私怨に近い動機があるのではないかという気がするのは思い過ごしか。ちなみにヴァンとしては妹に私怨を持たれるような出来事など、とんと心当たりが無い。
そうこう考えている間にも耳にちらつくのはナイトメア――第一音素譜歌――そこでヴァンは恐ろしいことに気がついた。
……待て。目の前に居るティアは歌など歌っていない。だが今この世界でユリアの伝えし譜歌を歌える者はヴァン自身を除けばティアしかいない筈だ。それにもかかわらず歌は続いている。しかもその歌声は間違いなくティアのものなのだ。
――ならば譜歌を歌っているのは一体誰なんだ!?
なものだからヴァンが混乱の極みになっても誰も彼を責められはしないだろう。その隙をティアが見逃すはずも無く一方的な攻撃が始まった。
「師匠っ!」
明らかに劣勢な師を前に、彼を慕うルークは自力で譜歌の影響下から抜け出しその元へと飛び出しかけたのだが、突如何者かにガシッと腕をつかまれ駆けつけることを許されなかった。一体誰が邪魔をと振り返ったルークの目に映ったのは……
「あらあら、駄目ですわよルーク」
いつも着ているの白と緑系の色を配色したドレスではなく、薄紫色のゆったりとしたドレスに身を包み、なにやらまばゆい笑顔でルークを見つめているナタリア。
「ナタリア……? って、なんでお前ウチにいんだよ!? しかも師匠がピンチだーって時に止めんなっつーのっ!!」
いつもは顔を合わせるたびに「あの日の約束を思い出してくださいまし!」とお願いしてるのだか脅してるのだか判らない勢いを持って詰め寄ってくる婚約者な彼女の事をルークは苦手にしていたのだが、今日の彼女はいつもの彼女とは違うと感じた。何しろ第一声が「思い出してくれましたの?」ではない。いぶかしむルークの仕草に、ナタリアは彼が先程の質問の答えを欲しているのだと判断した。
「あら、私が公爵家に顔を出すのはそんなにおかしいことではありませんでしょう?」
「……まぁ、そりゃそうか」
言われてみればそうだ。ナタリアは記憶を失う前のルークを余程慕っていたのか、理由がなくても頻繁にファブレ家へと顔を出しては記憶の有無を確かめていた。それに住んでいる場所もごく近くで親戚同士、そのうえ彼女はルークの婚約者なのだ。顔パスでないほうがおかしい。
「それに……貴方を止めたのは、アレに近づけてしまっては巻き込んでしまう危険があるからですわ」
「アレって……あの女の事か?」
「何を言っていますの。神託の盾の主席総長だなんて偉そうな肩書きを持っているくせに、彼女に情けないほど滅多打ちにされている髭の事に決まっているではありませんか」
「ひげって……」
「あの、ナタリア様。それは言い過ぎでは……?」
「さて……と、私も加勢するとしましょうか。――ガイ、体の自由が制限されているところ申し訳ないのですけれども、ルークのこと頼みますわね」
はいどうぞとルークをガイに預けると、ナタリアは事もあろうに未だ一方的な虐待の続くヴァンとティアの方へと足を向けた。その間にもティアの「ノクターナルライトっ、ノクターナルライトっ、ノクターナルライトっ!!」と連打する声がファブレ邸の中庭に響き続けている。時たま「バニシングソロゥ!」なんて声も混ざる。混乱と困惑から一つの抵抗もできないヴァンは傷だらけ。ティアの本業は音律士なのに一つも譜術を使っていないのが恐ろしいところだ。
ところでナタリアはどちらに『加勢』するつもりなのだろう?
そんなの考えるまでも無いとガイは疑問を斬って捨てた。
「ナタリア様。近づくのは危険――」
この場合一番危ないのはナタリアではなくきっとヴァンだと悟ってはいたが、相手が主の婚約者という場上言わないわけにもいくまい。
――すまないヴァンデスデルカ。俺は我が身が一番かわいい。
ガイだって早死にはしたくないのだ。
カツカツと背後から響いてきた靴音にティアは一旦攻撃の手を休めて振り返る。これが通常の状態であったなら無防備と取られかねない行動ではあったが、まだ譜歌は響き続けていたから問題は無い。
「ティア、貴女にしては生ぬるい攻撃ですわね。何故譜術を使いませんの?」
そしてナタリアの言葉にティアは確信する。このナタリアは共に旅をしたナタリアだと。
「譜術を使ったらいきなり終わってしまうでしょう? そんな事になったらみんなに悪いわ」
「まぁ、そういう事でしたの。けれど気にする事はありませんわ、貴女には十分その権利があると思いますわよ?」
「そう……かしら?」
やけに親しげに会話する彼女たちにヴァンは目を剥いた。もちろんその物騒極まりない内容にも。
ティアお前はいつの間に攻撃系の譜術を身につけたのだとか、何故ナタリア姫とそんなに親しそうなのかとか、というかみんなとは誰の事だとか際限なく湧いてくる疑問。
「ティア、ナタリア姫。何――をぐぅッ!!」
だから思わず声をあげてしまったのだが、ティアから返ってきたのは凍るような冷たい視線。そしてナタリアの返答はシャープネスと唱えてすかさず放った右ストレートだった。実は彼女の腕力、この場の中で2番目に強かったりする。そして本来、弓を扱うはずの彼女がこんな行動に出た理由はただ一つ。単に城から急いで屋敷にやってきたために弓矢を携帯していなかったから。それだけ。
「お黙りなさいヴァン。今は私とティアが話しているのです」
「そうよ兄さん。話の腰は折らないでほしいのだけど?」
二人は笑顔だった。だがヴァンは発見してしまった。二人のこめかみに血管が浮いていたことを。
ヴァンは後にリグレットに語る。「あの時、メシュティアリカとナタリア姫の背後に般若が見えた。リグレット、あの子はもうお前を超えてしまったかもしれん」遠い目をして語った彼に、副官であり彼に想いを寄せる者であったリグレットがどう思ったのか、それは語られることのない歴史である。
そしてナタリアの突然の凶行にルークとガイが心底怯えて震えていたりするのも蚊帳の外の出来事だった。
「あぁ、それと言っておきますが人違いです。私の名はメリルでしてよ。ナタリア・ルツ・キムラスカ・ランバルディアならば今頃、城で執務の真っ最中ですわ」
えぇっ、さっき自分でナタリアだって認めてたじゃねーかよ!? つーかメリルって何だよ?
この場に限ってルークは察しの良い子だったのでそう思っても口には出さなかった。これまで我慢とか遠慮というものを知らなかった彼にしてみれば珍しい反応。もっとも言おうものならきっと師と同じ目に遭うだろうと本能で察したからだろうが。
こうしてストレスを溜めながら人は大人になっていくのかもしれないなー……と思わずルークが呟いたら、隣に居たガイが今にも泣きそうな顔で頭をくしゃくしゃと撫でてくれた。彼もルークと同じ気持ちだったらしい。
「そういえばもう一人の貴方は何処にいらっしゃるの?」
「あの私、最初からここにいたのだけど……」
ナタリアが背にしていた建物の屋根の上から、歌うのを中断したもう一人のティアがちょっぴり寂しそうに呟いた。
「ご、ごめんなさいティア。私、気付かなくてっ!」
慌てて謝り倒すナタリアに「きっ、気にしないでくださいっ」とか細い声で過去ティアが慌てる。まさか一国の王女に――先程本人が否定したが、おそらく彼女も王女なのだろう――こんなにも親しげに謝られるとは思ってもみなかったのだ。
「けれどティア。何処で彼女と?」
「彼女が昇降機に乗った時よ。気がついたら私、彼女の前に立っていて……」
あちらも気がついたら自分にそっくりな人物が立っていた事に驚いたようで、思わずナイフの投げあいになったのだそうだ。けれどティアがとっさに狙いを外し、飛んできたナイフを避けたため双方に怪我は無かった。
「話を聞いたら兄さんを倒しに来たって言うものだから、一緒に来たの。あなたは?」
「私も似たようなものですわ。気付いたら私の部屋でもう一人の私と向き合っていましたの」
どうやらこれらの情報から考えるに、仲間たちは過去の自分の下へと飛ばされたらしいという結論に至った。となれば今ここに居なければならない人物が確実に一人欠けている。
「――という事はガイもこの辺りに潜んでいる可能性があるということね」
それならば私に任せてくださいなと、ナタリアが手をパンパンと打ちならして声高に叫んだ。
「――ガイ! 貴方の事ですから何処かから、こちらを見ているのでしょう? 弓矢を持ってきてくださらないかしら。私、いま無性に弓の鍛錬がしたいんですの!」
そして、しばしの静寂の後に困り顔で姿を現したのは弓と矢を携えた二人目のガイ。もちろん髪の短いルークもヒヨコの様にその後をついてきている。彼らはルークの部屋から出た後、今日がティアの襲撃の日だと気付いて今まで中庭に潜んでいたのだ。
「あのなぁナタリア。俺はもうファブレの使用人じゃないんだが」
「そうは言いつつちゃっかり弓矢持って来てる時点で説得力ねぇって。ガイ」
しかもガイが手にしているのは何故か闘技場の個人上級戦優勝商品のセレスティアルスター。うちにこんな弓あったっけ? 記憶にないその弓を見て髪の短いルークは首を傾げたが、まぁ一応ファブレ家は王族に連なっている上流階級だしこんな上等な弓があったっておかしくないよなうん。と、無理やり納得する。この家で弓を扱う人間に心当たりなど無かったから。
ちなみにルークやガイは言うに及ばず、ファブレ公爵の獲物は剣、白光騎士団たちも然り。メイドや他の使用人たちが武器を振るうことなど無いだろうから――あったとしても誰がこんな上級者向きの弓を扱えるというのか――やっぱり所有者は不明。美しい造形の弓だから飾り用なんだろうと納得したくても、隠しきれない使用の跡が窺われてとってもミステリー。追求はすまい。
「助かりましたわ、ガイ。弓が無ければこの髭が目の前に居るというのに一撃も与えられないなどという口惜しい思いをするところでしたもの」
さっき見事な右ストレートぶちかましてたじゃんなど愚かなツッコミを入れることはしない。ナタリアも気にしない。なぜなら彼女にとって『一撃』とカウントされるのは弓を使ったものだけだからだ。
ふとそれまで弓に夢中になっていたナタリアの視線が髪の短いルークの方へと向けられた。驚愕に目が見開かれる。
「まぁ、ルーク!? 本当にルークですの!?」
「あぁ、うん。まぁ……そうだけど。えと、ガイに聞いたけど2年ぶりって事になる……のか?」
……俺にしてみれば一日も経ってねーけど。
記憶が音素乖離したところでバッサリと切れているからか、それともガイやナタリアそれにティアの外見が見慣れているものとそう変わっていないのもあるのかもしれないが、どうも2年も経っているという気がしない。真新しい点と言えばガイとナタリアの服装が見慣れないものである事と、なんだかティアが前にも増して綺麗に見えるという点か。そういえばココには出会った頃のティアと、自分がいなくなって2年経ったティアがいるわけだが、二人とも同じ格好に同じ髪型で外見は同じだというのに何処かが違うとルークは感じた。
「あのさ、ナタリア――」
「もうっ、私やガイとばかり話していないでティアにも声をおかけなさい!」
バシィッ。
ナタリアは力いっぱいルークの背を叩いて、ティアのほうへと彼を突き飛ばした。
「……ルーク」
「ティア……」
片方は実に2年ぶり、もう片方は約一日ぶりの再会だった。
「感動の再会も果たされたことですし、もうそろそろ始めましょうか」
「へっ? 始めるって何を?」
ルークの疑問も何のその。彼以外の人間――ガイやティア――は了承済みらしく欠片も動揺は無かった。無言でガイに助けを求めても「見ていれば判るさ」としか返ってこない。
「ティア、一番槍は貴女に譲ります。思う存分やっておしまいなさい」
「ありがとうナタリア。……じゃあ、遠慮なく行かせてもらうわ」
チャキと杖を構え、すぅっと一つ深呼吸。唱える譜術は既に決まっている。
魔を灰燼と成す激しき調べ――
「天地に散りし白き光華よ、運命に従いて敵を滅せよ」
「待て、私はお前にとっての敵なのかっ!? メシュティアリカッ!!」
「――敵よ」
何を当たり前の事をとでも吐き捨てそうなティアの様子に、いささかシスコンの気のあるヴァンはたいそうショックを受けた。肉体的でなく精神的に。もう内心では男泣きである。
あぁ、可愛い可愛いメシュティアリカ。小さな頃から蝶よ花よと大事に大事に育ててきたメシュティアリカ。神託の盾に入ってからは忙しさのあまり、十分に可愛がってはやれなかったかもしれないが帰った時にはその空白を埋めるくらいには構い倒したメシュティアリカ。いつも兄さん兄さんと追いかけてきた健気で子犬のように可愛らしいメシュティアリカ。
彼の脳裏によぎるのは美しき日々の光景。思い出はいつも美しい。なんたって美化されるものだし。
「フォーチュン・アーク!」
そんな訳でイイ笑顔で動きを止めたヴァンにティアの秘奥義が炸裂。ヴァンは華麗に空を舞った。
「ちょ、ティア、今のはいくらなんでもちょっと酷いんじゃあ……。なんか師匠、真っ白に燃え尽きてるし」
「当然の報いよ。貴方がされた仕打ちに比べれば可愛いものじゃない」
一度は届いていたはずの兄の愛も今ではすっかり地に墜ちていた。まぁ自業自得という見方もあるのだが今のヴァンにそれが判るはずもない。
では次は私の番ですわねとナタリアがヴァンへ近づく。
「あぁ、そういえば貴方には父がお世話になっておりますわねヴァン謡将。お礼に他の方には滅多に見せない私の秘奥義をお見せしますわ」
―― 一番の特等席で。
満面の笑みでと共に付け足された一言に、数分前までのヴァンならば戦慄を覚えたことだろう。しかし、今の彼は妹にすげなくあしらわれ茫然自失中でナタリアの言葉など耳に入っていないに違いない。
「私の弓矢から逃れる事など許しませんわ! 降り注げ星光! アストラル・レイン!」
逃がれるどころかあの様子では逃げるという選択肢すらヴァンには浮かんでないんじゃなかろうかと、相変わらず長髪のルークと共に震えていた過去ガイは思った。
ドサッと重力に従い地面に叩きつけられたヴァンを見届け、やけにスッキリした表情でナタリアは息をつく。彼女から漂うのは何かをやり遂げた満足感と達成感。その後、そう時間が経たぬうちにすげない顔で事態を見守っていたガイに誘いの声をかけた。
「ガイ、貴方も一発。今までの恨みっつらみを晴らしませんこと?」
まるで声がかかるのを待ってましたと言わんばかりに彼に笑顔が戻る。
「それでは、お言葉に甘えて」
そしてまるで王の命を拝命する貴族のような――実際にナタリアは王族でガイは貴族だ――優雅な礼を一つ。流れるような動作でスラっと腰に佩いた剣を抜き放った。
もはや同郷とか幼馴染とかかつての同士という事実は忘却の彼方に捨て去ったガイに、ヴァンへの容赦など欠片もない。かつてファブレ家へ復讐を誓いルークやファブレに対して抱いていた憎しみもすっかり整理し終えた今のガイが胸にするは、ルークの育ての親兼心の友権使用人として彼を慈しみ将来を案じる想いのみ。
ならば未来の一端を知る者として、目の前に転がる人物を前に何もしないなどという選択肢を取る事は許されない。
「――気高き紅蓮の炎よ、燃えつくせ! 鳳凰翔天駆ッ!!」
手加減するなどという考えはもちろん論外だ。
「さぁルーク、あなたも。遠慮なんてすること無いわ」
「うーん。なんていうかここまでボコボコにされた師匠に追い討ちかけるのもなぁ……」
ルークは目の前でボロ雑巾のように地に伏す、かつては盲目的に憧れていた師の姿に同情を禁じえない。今はもう完全に決別した師ではあるが、それでも尊敬する気持ちは未だに持ち合わせているのだ。だからちょっぴり可哀相だなぁと思わないことも無いが……
流石にこんなになった師匠にロスト・フォン・ドライブぶち込むのは可哀想だし。あ、いま俺ってローレライの鍵どころか剣すら持ってねーから無理じゃん。じゃぁレイディアント・ハウルでも撃っとくか?
真っ先に浮かんだ選択肢が己の持ちうる中で最大の攻撃力を持つ技である時点でルークも鬼だった。もしかすると本人の気付いていない無意識とか潜在的な所で恨みを抱いていたのかもしれない。
「じゃ、師匠っ、恨まないでくれなっ!! レイディアント・ハウルッ!!」
その証明というべきか、彼の放った秘奥義はともすれば第二超振動に匹敵するかもしれない威力だったそーな(心の友権使用人談)。
もう一人のティアが譜歌を歌うのをやめた為か、若干屋敷の内部が騒がしくなってきていた。あちらこちらから「侵入者だ!」とか「曲者だ!」という叫びが聞こえてきている。白光騎士団がこの中庭に突入してくるのも時間の問題かと思われた。
「まずいわ。譜歌の効果が切れ始めているみたい」
「……なぁ、このまま俺たちがここにいたらややこしい事になんねぇ?」
短い髪のルークが心配そうに呟いた。
「そうだな。ルークは二人いるし俺も二人、襲撃者のティアも二人いて、ヴァンはボロボロ……」
「城にいますけれど、私も二人いますわ。一応、もう一人の私にはできるかぎり状況を説明しましたが……」
「この状況だといくら私たちが正しくても信じてもらえないでしょうね。兄さんはファブレ公爵や陛下に無駄に信頼されているもの」
それにいくらナタリアが王女だとはいえ、こうも同じ顔が並んでいては庇いきれまい。そして彼らがここに至った理由は突拍子が無く、事情を知らないものが聞いても絵空事と鼻で笑われるのがオチ。ヴァンに付け入られる隙はいくらでもあった。
「となれば屋敷から脱出しなければなりませんわ。ですが……」
七年前にルークの軟禁が決定して以降、この屋敷の間取りには若干手が加えられ外への出口が極端に少くなっていた。そのため恐らく出口は既に封鎖されていることだろう。このメンバーならば強行突破も可能だろうが、例え脱出できてもファブレ公爵家は王城に近い上に王家と血の繋がりがあるという性質上警備が厳重だ。さすがに街の外まで逃げきる自信は無い。
「ルークとティアの擬似超振動でなんとかならないか?」
ほら、前回はその手でルークたちが飛ばされたろ?
少し自信なさげにガイが提案する。自信が無いのは、果たして擬似超振動を起こした当人以外も一緒に飛ばされることができるか、そして同じ場所に到達することができるのか確証が持てないからである。
「みんなで逃げる分には問題無いと思うわ……多分」
「けど俺、剣もってねーけど」
「もう一人の貴方に借りればいいでしょ。剣っていっても木刀だけれど」
ぶっちゃけ第七音素を干渉させ合えればいいので別に使用するのは真剣でなくても良いのだ。もっと言えば武器で無くても第七音素を干渉させあうことは可能なのだが、ここはノリというやつである。
「この際ですから、もう一人のルークたちに実行してもらいませんこと?」
長髪のルークも連れて行くことは既に暗黙の了解にして決定事項だった。なにしろこのまま屋敷に置き去りにしては、ヴァンにしろキムラスカにしろどんなチョッカイを出されるか判ったものではない。特に今の長髪のルークではヴァンの甘言にコロッと騙されてしまうだろうというのが共通見解。不本意ながらも短髪のルークですら同意しているのだから確実に起こりうる事であった。
「おーい、ルーク。こっちに来てくれないか」
呼び出し係は比較的警戒の薄そうなガイ。人選が効を奏したのか、ほんの少し恐る恐るといった体ながらも長髪のルークがこちらにやってきた。そして動きの指導は短髪のルーク。これはティアやナタリアが視線を向けただけで、彼が目に見えて怯えるのが判明したためだ。
「その木刀構えててくれ。んで構えたら動かないでくれると助かる」
「へ? あ、ああ良いけどよ」
先程、部屋で会ったとはいえ同じ顔、同じ声の人間にやはり戸惑いを隠せないながらも素直に従う長髪のルーク。前の自分は酷かったと公言して憚らなかった短髪のルークだったが、その素直な様子に僅かに驚いた。酷い酷いと言ってきたけれどもしかして自分は、今の自分はもちろん前の自分の事も卑下しすぎていたのではないだろうか?
前の自分にだって良いところは少なからずあったのかもしれない。その証拠にイオンは最初の頃からルークの事をいろいろと気にかけ、時には褒めてくれていたではないか。
「……んだよ、何か言いたい事があるんなら言えっつーの」
声にハッと我に返ると、胡乱な目でこちらを見ている長髪のルーク。今度は短髪のルークが戸惑う番だった。どうも考え事をしていた間、ずっと彼を凝視していたらしい。
「えと、言いたい事なんかは特に……無いけど」
「なら人のこと凝視してんじゃねーよ。んなことしてるヒマがあんならサッサと準備しろっての! 何がなんだかわかんねーけど俺が手伝ってやってんだぞ!」
高圧的な物言いに自分の事ながら「やっぱさっき考えたのナシ。こいつ最低」と思い直すルークだった。けれど彼のいう事ももっともだったので気持ちを切り替え作業に戻ることにする。
「おーい、ティア。お前もこっち来て杖、構えてくれねぇ?」
ちなみに呼んだのは未だ屋根の上にたたずむ過去ティアの方である。彼女も脱出させなければ侵入者として捕らえられてしまう。
「……こんな感じで良いかしら?」
「ああ。んで、合図したら思いっきりルークの木刀に振り下ろして欲しいんだけど良いか?」
ええ。と肯定の返事に満足して。短髪のルークが他の仲間たちに準備オッケーだぞーと声をかける。
準備は万端でいざ合図を出そうとしたその時――
「待てっ、お前たちルークをどうするつもりなんだ!?」
ハッとここに至って通常の思考を取り戻した過去ガイが、至極最もな声をあげた。それに答えたのはティアでもナタリアでもなくガイ。彼はこれから公爵子爵を誘拐するというのに飄々とした様子。
「ずっとこの屋敷にいるのはルークの教育上良くないからなぁ。しばらくは社会勉強がてらに外でも回るつもりさ。さしあたっては買い物の仕方でも学んでもらうかな」
茶目っ気を感じさせる物言いだったが、一人だけ不満を露にした人物がいた。
「ガイ~、あんま蒸し返すなよー。未だに恥ずかしいんからな」
「けど、事実でしょ」
「う。けど、いつまでも人の失敗をあげつらうのは人が悪すぎだっつーの!」
ティアの指摘に、頬を膨らませてそっぽを向いてしまったルーク。そのやり取りを聞いていたガイがじぃ~んと涙を目に溜めたかと思うと感極まった様子でナタリアに詰め寄った。
「ナタリアっ。ルークが! ルークがあげつらうなんて難しい言葉を!!」
「あー、はいはい。私も聞きましたから落ち着きなさい、ガイ」
「フェレス島でも無辜なんて難しい言葉を使ってたし、やっぱりウチのルークは賢い子だよなっ、なっ?」
「~~~っ、ガイ! 恥ずかしいからそういうのやめろって!」
「……全く。ガイの親馬鹿にも困ったものですわ」
「いいじゃない。こんなに嬉しそうなガイは2年ぶりだもの」
「ふふっ。こんなに楽しそうなティアを見るのも2年ぶりでしてよ?」
一方、そんな光景を眺めていた長髪のルークたち。
「……なぁ、冷血女。俺たちいつまで構えてればいいんだろーな?」
「……さぁ? 私に聞かれても知らないわ。それと私の名前は冷血女じゃなくてティア・グランツよ」
長い髪のルークの言葉をちょっとだけ自信なさげに否定し、名を告げる過去ティア。冷血女と呼ばれるにふさわしい所業を成したティアそっくりの女性の名もまたティア・グランツ。ならばどうして自分が彼女のようにならないと言い切れるだろう。その心中は複雑だった。
「……そか。その、なんつーかお前はあんな風にはなんなよ? マジ怖ぇから」
「……努力はするわ。あなたこそ、あそこの彼みたいに怪我人に情け容赦なく技を振るう人にはならないようにね」
「だっ、誰がんなひでぇマネするかよッ!」
「……まぁ、大丈夫……なのかしら………?」
――とりあえず、一行は白光騎士団が突入してくる前にファブレ家から脱出できたそうな。